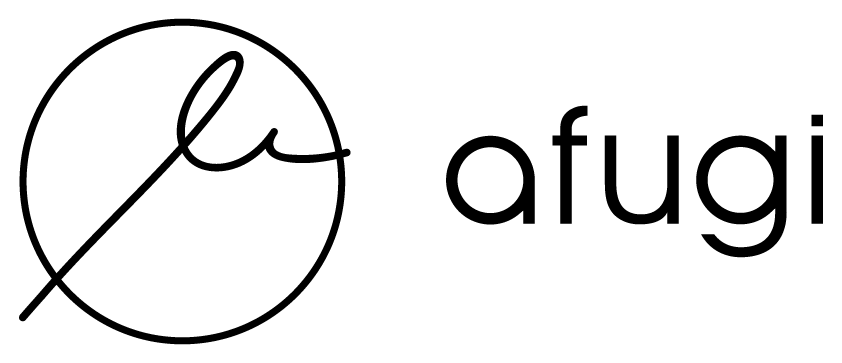やきもの散歩道

常滑焼の産地としても有名な愛知県常滑市。
瀬戸、信楽、越前、丹波、備前と並び、日本六古窯のひとつでもある歴史ある窯元産地です。


知多半島の西側に位置し、少しいけば伊勢湾も近い、湾岸部と山間部が存在するエリアで常滑焼は発展していきました。
市内はまさに「やきものの街」
あらゆるところで「常滑焼」を感じさせる魅力ある街並みです。
常滑駅がある平地から山間部に向かっていくと「やきもの散歩道」があります。
散歩道の途中には、いろんな窯元さんや資料館、カフェなどもあるので、1周するだけでいろんな目線で常滑焼を楽しめます。

<やきもの散歩道の地図>
常滑焼は招き猫が有名。
常滑駅からやきもの散歩道に向かう途中にはたくさんの招き猫が。

いろんな招き猫がいるので、道を歩いてるだけでも楽しめます。
スタートは「陶磁器会館」
ここでも招き猫が招いてくれます。

陶磁器会館入口の郵便ポストの上にも猫が。

やきもの散歩道スタート。

早速道の途中には、赤褐色のツボが並んでいます。

趣のある石段や小道も。


雰囲気のある古い家屋や煙突が見えてきます。


特大のとこにゃんへ寄り道。

歴史を感じる街並みや石畳が見えてきます。

途中には「だんご茶屋」さん

小休憩して、小道を歩いていきます。

歩いていくと「廻船問屋 瀧田屋」の家屋。

ツボが並ぶ坂道沿いにあっていい雰囲気。

瀧田屋さんを覗いたらいよいよ
やきもの散歩道の代表的なスポット「土管坂」へ!

左右が土管の壁!!


土管坂のあとは登窯がまっています。
まずは登窯広場へ。

広場には展示工房館もあります。

さらに歩き進めると登窯の登場。

登窯がそのまま残っています。



「焚き口」
当初の登窯は薪材や松葉を燃料としていましたが、明治後半には需要も増え、薪材や松葉が不足気味になり、これに代わる燃料として石炭が用いられるようになりました。
しかし、石炭窯を製造するには多額の資本を必要とするため、在来の登窯を利用し、石炭を使い燃料費の節約を図ろうとしました。
この改良は第一室の焚き口(ホクボ)を従来の1つから数個の焚き口にわけ、それぞれロストルをつけ石炭の燃料を容易にしたものであり、これにより第一室の焼成を石炭、第二室以降の焼成を薪材や松葉によって焼成する、いわゆる折衷室に改良されました。
第一室では約4昼夜全室を焚き終わるのに11日くらいかかりました。
登窯を抜けると、再び昔ながらの雰囲気の家屋と小道に。

窯が昔のまま残っています。


猫。

小道がつづき、散策気分で楽しめます。


古い家屋や小道がつづき、歩いているだけでも歴史ある雰囲気が。

カフェや陶器屋さんなど、お店が並んでいます。
歩いた記念の器探しにはおすすめ。

ゴール!!
休憩をはさみながらゆっくり歩くと半日はかかるくらいの散歩道です。
日本六古窯のひとつだけあり、歴史ある焼きもの産地。
エリアはそこまで広くはなく、エリア内にギュッと詰め込まれたような独特な街並みです。
ぜひやきもの散歩道で、歴史を感じる散歩をお楽しみください。
常滑焼といえば「招き猫」と「急須」
やきもの散歩道にもたくさんいるくらい、常滑焼は招き猫が有名で、生産量も日本一。
そして招き猫だけでなく、壺、お椀など、時代の変遷とともに様々なものを生産してきました。
しかし、招き猫だけではなくもうひとつ日本一があります。
それが急須。
急須の国内シェアはなんと90%。
急須の一大産地となっています。
急須に適した耐久性が高い常滑の土
急須づくりが盛んになった所以の1つでもあるのが、常滑の土の「耐久性」です。
常滑の土の高い耐久性により、「水を吸わない」特徴が急須に適していたのです。
常滑急須は高い技術力で作られており、美味しいお茶が入れられるとして高い人気を誇っています。
手作りだからこそ楽しめる朗らかな雰囲気や優しい表情が魅力です。
急須はそんな常滑焼で、歴史とともにお茶をお楽しみください。