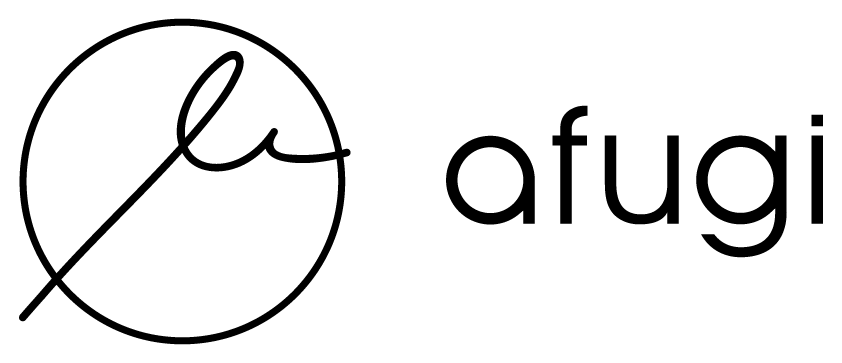木のまな板 | メリットとデメリットとは?素材別の特徴や魅力とお手入れ方法を解説 [前編]

木のまな板 | メリットとデメリットは?素材別の特徴や魅力とお手入れ方法を解説
「あなたに合ったまな板で料理を楽しもう」
現在ではプラスチック製やゴム製など、素材の種類が豊富なまな板。
素材によって特徴や調理の仕方が変わるので、料理に合わせて素材を選ぶと料理のしやすさが変わります。
その中でも、木製のまな板は人気のアイテム。
他の素材と比べると少し値段もはりますが、値段以上に満足度が高いと感じる方も多いようです。
天然素材のため温かみがあったり、木製ならではの雰囲気がキッチンをおしゃれにしてくれる一方で
他の素材よりもお手入れや扱いに手間がかかるのでは?
と感じてしまうことも。
「値段以上に愛されるその理由とは?」
「お手入れの注意点とは?」
「木製ならではの特徴とは?」
今回は、木製のまな板のメリットやデメリット、素材の種類や選び方、お手入れ方法について解説していきます。
木のまな板選びの参考になれば幸いです。
本記事の内容:
・まな板の素材の種類と特徴
・木のまな板の特徴
・メリット
・デメリット
・木のまな板の魅力
・取り扱いの注意点
・お手入れ方法
まな板の素材の種類と特徴

冒頭でお伝えしたように、まな板にはたくさんの種類があります。
よく使われているのは「プラスチック製」「ゴム製」そして「木製」が挙げられます。
プラスチック製
ポリプロピレン、ポリエチレン、ABS樹脂などが一般的に使われています。
【メリット】
「軽い」→持ち運びや収納がしやすく、調理時に扱いやすい
「お手入れ簡単」→水を吸収しないため洗いやすく、乾きやすい。高温洗浄が可能なタイプもある
「衛生的」→カビや雑菌が繁殖しにくく、熱湯消毒や漂白剤の使用が可能
「お手頃価格」→木製やゴム製のまな板に比べて安価なものが多い
「デザイン・カラーが豊富」→食中毒リスクの軽減で食材ごとに色分けして使い分けが可能
【デメリット】
「傷つきやすい」→包丁の刃による細かい傷がつきやすく、そこに雑菌が入り込むことがある
「変形しやすい」→熱に弱く、高温で変形したり反ったりすることがある
「包丁を傷めやすい」→硬めの素材のため、木製のまな板に比べて包丁の切れ味が落ちやすい
「吸着力が弱い」→滑りやすい素材のため、調理中に動きやすいことがある(滑り止めが必要)
「劣化が早い」→長期間使用すると変色したり、ニオイが付きやすくなったりする
【お手入れ方法】
・食器用合成洗剤とスポンジで洗う
・汚れや臭いが気になる場合は台所用漂白剤を使う
プラスチック製のまな板は定期的に交換することが推奨されます。
特に傷が多くなった場合や、黒ずみ・ニオイが取れなくなったら買い替えのタイミングです。
ゴム製
主に合成ゴムや天然ゴムを使用
【メリット】
「包丁にやさしい」→適度な弾力があり、包丁の刃が傷みにくい
「耐久性がある」→傷がつきにくく、木製やプラスチック製に比べて長持ちしやすい
「耐水性がある」→水を吸収しにくく、カビや細菌が繁殖しにくい
「滑りにくい」→まな板自体がしっかり密着し、調理中に動きにくい
「お手入れ簡単」→木製のように手入れが難しくなく、プラスチック製よりも劣化しにくい
「熱湯消毒が可能」→熱に強く、煮沸消毒や漂白剤の使用ができる
【デメリット】
「価格が高い」→プラスチック製や一般的な木製よりも高価
「重さがある」→プラスチック製より重く、大きいものは扱いにくい
「油汚れが落ちにくい」→ゴムの特性上、油を吸着しやすく、ベタつきやすい
「独特のにおいがすることがある」→新品時や長期間使用後にゴム特有のにおいが気になる場合がある
「食洗機非対応」→高温に強いが、食洗機の強い水流や高温乾燥で劣化しやすい
【お手入れ方法】
・食器用合成洗剤とスポンジで洗う
・汚れや臭いが気になる場合は台所用漂白剤を使う
ゴム製まな板は、耐久性と包丁への優しさを兼ね備えたバランスの良いまな板です。
プロの料理人にも人気がありますが、適切な手入れをしないと油汚れやにおいが気になることがあります。
また、変形するまな板は、食材を鍋やフライパンに入れやすいので、料理中のストレスを軽減する場合もあります。
木のまな板の特徴

木のまな板は、主にヒノキ、イチョウ、ブナ、桐、メープルなどの天然木が使用されています。
【メリット】
「刃にやさしい」→適度な弾力があり、包丁の切れ味が長持ちする
「傷が自然に回復しやすい」→木の繊維が自己修復しやすく、傷が目立ちにくい
「抗菌・防臭効果がある」→ヒノキやイチョウなどは天然の抗菌作用があり、雑菌が繁殖しにくい
「滑りにくい」→木の質感が手になじみ、調理中に安定しやすい
「見た目が美しい」→自然素材ならではの高級感や風合いが楽しめる
「静音性が高い」→切るときの音がソフトで、金属音が響きにくい
【デメリット】
「水に弱い」→吸水性が高いため、乾燥不足でカビや黒ずみが発生しやすい。乾燥やお手入れが重要
「お手入れが必要」→使用後はしっかり乾かす必要があり、漂白剤の使用は木を傷める可能性がある
「重い」→プラスチック製やゴム製に比べると重量があり、持ち運びや収納がやや不便
「食洗機非対応が多い」→高温や長時間の水浸しで割れや反りが発生する可能性がある
「値段が高いものが多い」→良質な木材を使用したものは価格が高め
「油染みがつきやすい」→木の繊維に油が染み込みやすく、一度つくと落ちにくい
【お手入れ方法】
・粉末クレンザーとたわしで洗う
(食器用合成洗剤に含まれる界面活性剤はまな板の黒ずみの原因となるため)
・黒ずみや臭いが気になる場合は輪切りにしたレモンでこする
・熱湯や消毒用アルコール(エタノール)を吹きかけることで黒ズミやカビを未然に防ぐことができる
特定の商品ではなく、あくまで一般的なまな板の材質毎にメリット・デメリットとお手入れ方法を簡単にまとめてみました。
木製まな板は適切なお手入れをすれば長く使えます。
使用後はしっかり洗って水気を拭き取り、風通しの良い場所で乾燥させることが大切です。
特にヒノキやイチョウはプロの料理人にも愛用されるほど使い心地が良く、包丁を大切にする人にはおすすめです。
| プラスチック製 | ゴム製 | 木製 | |
|---|---|---|---|
| 刃当たり | × | ○ | ◎ |
| 安定性 | × | △ | ◎ |
| 耐久性 | △ | ○ | ◎ |
| お手入れ | ○ | ○ | △ |
| デザイン | ◎ | △ | ○ |
| 価格 | ◎ | ○ | △ |
木のまな板の魅力

それぞれ素材によってメリットやデメリットがある中で、木のまな板には他素材にはない魅力があります。
プロの料理人が愛用していることが何よりの裏づけになりますが、包丁や環境にやさしく、長く使える使いやすさと機能面が優れていることが最大の魅力といえます。
自己修復ができるように、天然素材のため育てることができます。
傷もアジになります。
育ち方は普段の使い方で変わるため、使う人によって育ち方が変わるということです。
そして何より、包丁で食材をカットするときの「心地よさ」があります。
不快にならない心地いいカット音は病みつきになるかもしれません。
料理がもっと楽しくなる心地よさは、「長く使える」という点においては、木のまな板は他素材と比べて群を抜いているといえるでしょう。
>>「木のまな板はどんな素材をがおすすめ?」素材の種類や特徴はこちらでまとめています。
木の種類によって特性も異なりますので、素材選びの参考にどうぞ。
木のまな板の使い方

使い方①:使う前に水で軽く濡らす
水を吸わせることで、食材のニオイや色素が染み込みにくくなります。
乾いたまま使うと、油や汁が染み込みやすいので、特に油ものを調理する際は使用前に軽くみずを濡らしてから使うようにしましょう。
使い方②:食材ごとに使い分ける
肉・魚用と野菜用で分けると、ニオイや菌の移りを防止できます。
1枚で使う場合は、肉や魚を切った後に熱湯消毒すると安心です。
使い方③:安定した場所で使用する
まな板が滑る場合は、濡らした布巾や滑り止めシートを下に敷くようにしましょう。
使い方④: あくまで包丁の刃にやさしく
刃にやさしい木のまな板ですが、強く叩きつけるように切ると、刃こぼれしやすくなります。
スムーズな切れ味を保つために、刃を滑らせるように使いましょう。
木のまな板の取り扱いについて

木のまな板の特徴で簡単に触れましたが、木製のまな板を使う上での注意点を解説していきます。
長く使えるからこそ、注意点もしっかり理解しておきましょう。
注意点①:長時間水につけない
吸水性があるため、つけ置きをすると変形やひび割れの原因になってしまいます。
水に長時間つけるのは避けましょう。
注意点②:直射日光に当てて乾かさない
急激な乾燥で反りやひび割れが発生することがあります。
風通しの良い環境で陰干しするのが最適です。
注意点③:漂白剤の使用に注意
酸素系漂白剤(過炭酸ナトリウム)なら比較的安心して使えますが、塩素系漂白剤は木を傷める可能性があるので控えましょう。
注意点④:食洗機・乾燥機はNG
自然乾燥で十分乾きます。
高温と乾燥でひび割れや反りが発生しやすいので、これらの使用は避けましょう。
注意点⑤: 油が染み込みやすい
油分の多い食材を切るときは、事前に水で濡らしておくと染みにくいです。
木のまな板のお手入れ方法

長く使っていくためにも、取り扱いの注意点とともにお手入れ方法もマスターしておきましょう。
毎回のお手入れ:
①すぐに洗う → 使い終わったらすぐに洗剤で洗い、しっかりすすぎましょう
②熱湯をかける → 雑菌を減らし、消臭・除菌効果が期待できます
③水気を拭き取る → 乾いた布で水分をしっかり拭きましょう
④風通しの良い場所で陰干しする → 立てかけて乾燥させるとカビ防止になります
黒ずみ・カビ対策:
・塩+レモン or 重曹 → 黒ずみ部分をこすり洗いしましょう
・熱湯消毒 → 週に1回程度、熱湯をかけて除菌しましょう
・サンドペーパーで削る → 深い傷や黒ずみが取れないときに有効です
長持ちさせるために:
・定期的に表面を削る(かんな削りを依頼すると新品同様に)
・木の種類に合ったお手入れをする(ヒノキやイチョウは乾燥に注意)
木のまな板は
「こまめに洗ってすぐに乾かす」
と覚えておくといいかもしれませんね!
まとめ
木製まな板は、適切に使い、お手入れすれば長く使えるアイテムです。
一見、お手入れや使い方が面倒と思うかもしれませんが育てる楽しさがあります。
メンテナンスも含めて木製まな板を楽しめるともいえます。
こまめに洗ってすぐ乾かすことさえ気をつければ、ずっと快適に使うことができます。
お気に入り木のまな板があるだけで、毎日の家事が楽しくなります。
自分に合ったまな板が見つかれば、ストレスを感じることなく料理を楽しむことができます。
「木」という雰囲気がインテリアとしても楽しませてくれます。
木のまな板のある生活で、いつもよりちょっとだけ心地よく快適な暮らしをお過ごしください。
関連商品
関連情報
産地を温ねて心づく日本製
「産地を温ねて心づく日本製」
産地を訪ねる
歴史や文化を温ね
いろんな職人技に心づく
各地の素晴らしい伝統産業や職人技術で
心地よく豊かなライフスタイルを
ご提案致します。
「たずねる。心づく。豊かな暮らしを。」
<MADE IN JAPAN>
| brand | afugi |
|---|---|
| online store | https://afugi.net/ |
| open | online 24h |
| tel | 03 6820 2079 |
| contact | info@afugi.net |