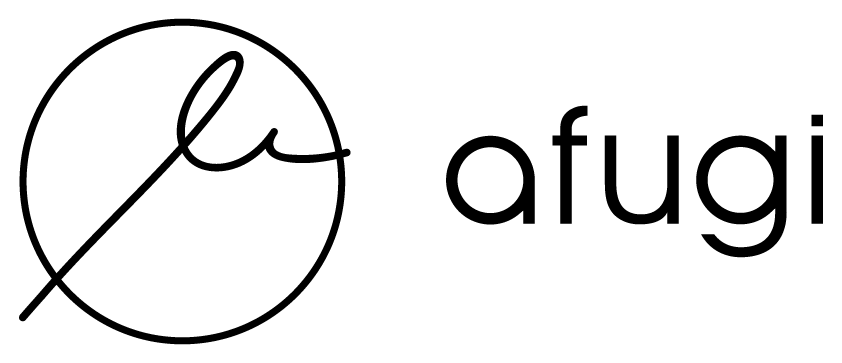木のしゃもじのメリットとデメリットを徹底解説!木製しゃもじとの上手な付き合い方とは?

木のしゃもじのメリットとデメリットを徹底解説!
木製しゃもじとの上手な付き合い方とは?
「木の風合いを楽しみたい」
「木のしゃもじだと美味しそうに感じる」
「炊飯器の内釜を傷つけたくない」
最近はプラスチック製やフッ素樹脂加工のものも多いですが、このような理由から「木のしゃもじ」を愛用するファンも根強くいらっしゃいます。
でも、木のしゃもじって
「なんとなく良さそう」
というイメージだけで使っていませんか?
・そもそもなんで木がいいの?
・手入れが大変そうだけど、実際どうなの?
・カビが生えたりしないの?
木のしゃもじは面倒な手入れこそありませんが、長く使えるからこそ、上手に付き合っていく必要があります。
今回は、そんな木のしゃもじのメリットと、知っておくべきデメリットや注意点を、具体例を交えながら徹底的に解説します。
・木製しゃもじを検討している
・買ったけどどうメンテナンスすればいいのかわからない
少しでもそんな方の参考になればと思います!
木のしゃもじのメリット
木のしゃもじには、プラスチックをはじめ、他の素材にはない特徴がたくさんあります。
まずは木のしゃもじのいいところを5つご紹介します。
メリット①:ご飯粒がくっつきにくい
木のしゃもじの最大の魅力。
木材には、適度な調湿性(湿気を吸ったり吐いたりする性質)があるので、ご飯粒がくっつきにくいんです。
この性質のおかげで、ご飯の表面から出る水分をほどよく吸収・放出し、しゃもじの表面でベタつきがちなご飯粒をさらりと剥がれやすくしてくれます。
炊きたてのご飯をよそう際、プラスチック製だと表面に水膜ができてご飯が張り付きやすいのに対して、木は表面の凹凸(微細な気孔)が水分をキャッチし、ご飯がまとわりつくのを防いでくれるんです。
メリット②:炊飯器の内釜を傷つけにくい
木の素材は適度な柔らかさがあるため、フッ素樹脂加工された内釜を傷つける心配がほとんどありません。
内釜のコーティングが剥がれてしまうと、性能が落ちるだけでなく、異物が混入するリスクも高まります。
炊飯器を長く使うためにも木のしゃもじはおすすめです。
メリット③:手へのなじみと「ぬくもり」を感じる
木は熱伝導率が低いため、炊きたてのご飯の熱が手に伝わりにくく、快適に使用できます。
また、手触りがやわらかく、使い込むほどに手に馴染んでくるのも魅力のひとつ。
「調理器具に愛着を持ちたい」という方にはピッタリです。
メリット④:静電気が発生しにくい
プラスチック製のしゃもじは静電気を帯びやすく、そのせいでご飯粒がくっつく原因にもなります。
その点、天然素材の木は静電気が発生しにくいため、ストレスなくご飯をよそうことができるんです。
メリット⑤:抗菌・防カビ効果をもつ樹種がある
木のしゃもじで使われがちな「ひのき」や「さわら」といった樹種には、カビや雑菌の繁殖を抑える天然の成分が含まれています。
とくに「ひのき」はまな板にも使われるように、その抗菌性の高さが魅力です。
衛生面においても優れているんです。
木のしゃもじのデメリット
メリットが多い木のしゃもじですが、もちろん「ここは気をつけないと!」という点もあります。
知っておきたい3つの注意点をご紹介します。
デメリット①:水分を吸いやすく、カビや黒ずみのリスクがある
木材の調湿性はメリットである反面、使用後にしっかり乾燥させないと水分を吸いすぎてしまい、カビや黒ずみの原因になります。
「手入れが大変そう」という不安は、多くの方が抱く疑問ですよね。
とはいえ、面倒な手入れは必要ありません。
使用後すぐに水洗いをしてしっかり乾かすこと
です。
洗った後は、風通しの良い場所でしっかりと自然乾燥させましょう。
つけ置き洗いは厳禁です。
デメリット②:強い洗剤や食器洗い乾燥機は避ける
木のしゃもじは、洗剤を吸い込んでしまうと匂いが残りやすいという性質があります。
食器洗い乾燥機の高温・急乾燥は木材を歪ませたり、割れさせたりする原因となります。
基本は水またはぬるま湯で洗い流すだけでOKです。
どうしても油分などが気になる場合は、中性洗剤を少量だけ使い、素早く洗い流してください。
デメリット③:匂い移りの可能性がある
木のしゃもじは水分を吸収する性質があるので、ご飯以外の料理(お鍋の具材を混ぜるなど)に使った際、その匂いが木に残ってしまう場合があります。
ご飯用のしゃもじは、ご飯専用として使い分けるようにしましょう。。
また、匂い移りしにくいとされる桜や朴(ほお)の木を選ぶのもひとつの手です。
あなたにぴったりの木のしゃもじを見つけよう
木のしゃもじはご飯をより美味しく、心地よくいただくための道具です。
注意点さえ知っておけば、劣化ではなく馴染んでいくので、長く使うことができます。
とはいえ木の素材によって特徴があります。
木のしゃもじを選ぶ際は
・「樹種」で選ぶ
カビ・抗菌性を重視するなら
「ひのき」「さわら」
東濃ひのき | しゃもじ 23cm スリムで使いやすい東濃ひのきのしゃもじ SALIU [岐阜]
販売価格
¥ 1,430 (税込)
商品紹介
匂い移りが少なく、硬めで丈夫なものなら
「桜」「朴(ほうのき)」
付知山桜 | しゃもじ 23cm スリムで使いやすい山桜しゃもじ SALIU [岐阜]
販売価格
¥ 1,430 (税込)
商品紹介
・「加工」で選ぶ
木目を生かした無塗装のものがご飯粒がつきにくいとされますが、手入れに自信がない場合は、オリーブオイルなどで表面をコーティングした「オイル仕上げ」のものを選ぶと、水分の染み込みを軽減できます。
・「形状」で選ぶ
ご飯を潰さずに切るように混ぜやすく、よそうのに適した「丸みがあり薄いもの」や、握りやすくて滑りにくい「持ち手の形状」ものを選びましょう。
木のしゃもじを長持ちさせる簡単ケア
木のしゃもじを使う時はこれだけ!
使用後すぐに水洗いをしてしっかり乾かすこと
ご飯粒が乾いてこびりつく前に、すぐに水で洗い流しましょう。
洗った後はふきんで水気を拭き取り、上向きで立てかけず、横向きに置いて(接地面を少なくして)風通しの良い場所で完全に乾かしましょう。
木のしゃもじは、手をかければかけるほど、深みのある色艶が増し、あなたにとって唯一無二の存在になってくれます。
プラスチック製のものと比べると注意点はありますが、その手間以上にもたらしてくれるメリットがあります。
美味しいご飯は木のしゃもじで。
素敵に食事を楽しみましょう。
関連商品
関連情報
産地を温ねて心づく日本製
「産地を温ねて心づく日本製」
産地を訪ねる
歴史や文化を温ね
いろんな職人技に心づく
各地の素晴らしい伝統産業や職人技術で
心地よく豊かなライフスタイルを
ご提案致します。
「たずねる。心づく。豊かな暮らしを。」
<MADE IN JAPAN>
| brand | afugi |
|---|---|
| online store | https://afugi.net/ |
| open | online 24h |
| tel | 03 6820 2079 |
| contact | info@afugi.net |